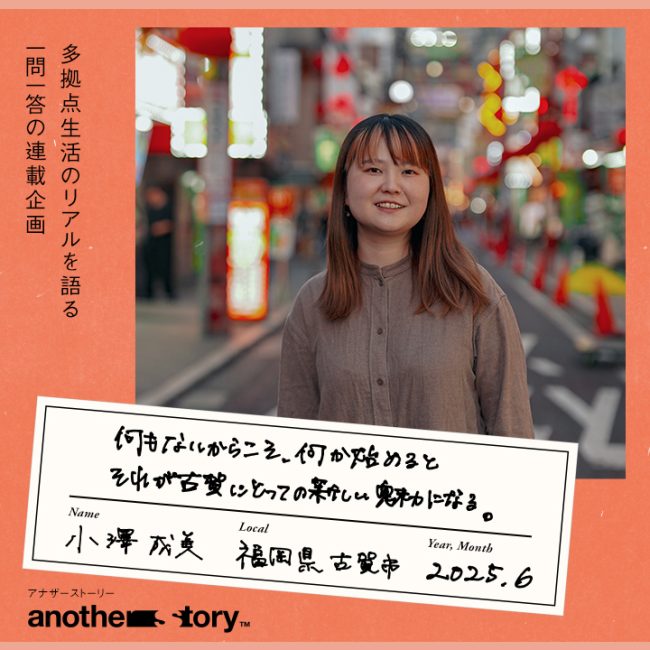Melbourne Life
#01
なかなか決まらない
引っ越し問題
建築家、西田 司、この春より初の海外生活に家族で奮闘中。
移住先はオーストラリアのメルボルン。
暮らしはじめて半年が経過し、そろそろ新生活にも慣れてきた頃、
不定期ですがメルボルンでの日常を連載で報告していきます。
初回は、決まらない引っ越し先と車のエピソードです。
@Melbourne, Australia

メルボルンの移住先に決まったレンガづくりの我が家
メルボルンは空室率は1%⁉︎
教鞭をとる大学のサバティカル制度で、はじめての海外生活!
とにかく毎日が新鮮な体験の連続です。
さっそく現地の暮らしぶりを……といきたいところですが、
その前に、メルボルン移住にあたり想定外に難題だったのがお引っ越し。まずはこの話題から。
日本でメルボルンの賃貸物件を仲介しているサイトを探すのはとても難しく、1ヶ月くらいのエアビー(Airbnb)ならあるのですが、年単位の長期滞在向け仲介サイトは検索してもなかなか見つからず、でした……。
頭を抱えていると、ちょうど大学時代の同級生がメルボルンに住んでいることを知り、さっそくコンタクトをとりました。彼には現地で家を借りる方法、賃貸物件の現状などをこと細かに教えてもらいました。
聞けば、最近のメルボルンの空室状況は約1%。空いてもすぐに埋まってしまうほどの人気だとか。そんな事情を知ってすこし不安になりましたが、とりあえず紹介してもらった現地の不動産サイトで物件探しからスタート。
ちなみちメルボルンで物件を内見する際は、日本のように1日にいくつもハシゴできるわけではありません。物件の内見は週に1枠と決まっていて、例えば木曜の16時30分から45分までの間が内見日であれば、希望者全員が当日に申し込みます。そして見て気に入れば、申し込みフォームに必要事項を記入。オーナー審査をクリアすると契約へと進めます。
申し込みフォームで答えることは、現在の年収や貯金額など。それと重要なのが後見人の存在です。日本で言えば保証人のようなもので、僕は今回、メルボルン大学の同僚の先生に後見人になってもらいました。日本の保証人制度と違う点は、仮に家賃を踏み倒しても、後見人に請求がいきません。
話を戻します。そんなわけで出国までに時間があれば現地の不動産サイトで調べる日々が続きました。
友人の話では、10物件以上内見しても審査結果ですべて落選だったこともあったそう。周りの知人に相談すると、海外で物件を探すならそれくらいは普通で、その間はエアビー生活だと言われる始末。これは全然決まらないのも覚悟のうえで、向こうに行ってから1カ月くらいは家探しの日々かなと思っていた時、「あきらめるにはまだ早い!」と急遽メルボルンに留学中の娘が協力してくれることに。
内見を彼女にお願いし、「どこどこが汚れている」「ここの外壁が傷んでる」などなど、お互いにLINE通話でやりとりしながら、藁にもすがる思いで審査に申し込むと、まさかの2物件目で契約が成立! これは本当にラッキーでした。

広々とした外構のアプローチは、レンガの温かな雰囲気に包まれている
いよいよ引っ越しがスタート!
契約が成立した物件には、4月5日から入居可能とのこと。
僕は、4月1日に家族よりもひと足早くメルボルンに向かい、エアビーで10日間宿泊。入居日の4月5日から10日までの間で、ベッド、ダイニングテーブル、ソファなどの家具類を購入し、暮らせる状態に自宅をセットアップ。家族は、それから2週間ほどして合流することになりました。

家具類は、すべて現地のIKEAで購入した
家の間取りは4LDK。1階は、ダイニングキッチンのほかに僕が仕事に使う書斎があります。2階は、3部屋あって、それぞれ子ども部屋として使っています。
建物の築年数は意外と古くて、レンガづくりの外壁には断熱材も入っていません。
庭のデッキスペースにテーブルがあるので、ここでよく食事をしたり、仕事をしたりしています。また休日には隣人宅から芝刈り機をお借りてして、芝生や植林など庭の手入れもします。

庭に面した開放感あふれるが屋外スペース

オーストラリアでは、2×4工法の木造住宅が人気。街中でも建築中の住宅をよく見かける
もったいない精神
暮らしはじめてほどなくすると、食器などの日用雑貨が必要になります(ちなみに日本から家財道具は持っていきませんでした)。
オーストラリアでは、「オポチュニティショップ」という名のチャリティショップをよく見かけます。これは地域のボランティアで運営する、いわゆるリサイクルショップ。寄付で集めた中古の雑貨類を低価格で販売して、その収益を福祉活動などに還元しています。我が家の食器類は一式こちらで揃えました。
オーストラリアに来て思うのは、人々に「もったいない精神」が根付いているということ。例えばフードロスの意識がとても高くて、カフェで出されるドーナツ、スーパーで売られているお惣菜など、夜7時までの営業であれば、閉店3、4時間前には売れ残りそうな食品を定価の1/3で販売しています。

近所の道端に処分されていたバスケットコートを車でピックアップ、さっそくガレージの一角に設置
先日、息子が前から欲しいと言っていたバスケットコートを、たまたま近所の家の前の道端で見かけたので、さっそく車のトランクに載せて持ち帰り、自宅のガレージに設置しました。オーストラリアでは、いらなくなった不用品を自宅前の道路脇に置いて、欲しい人に譲るという慣習があります。これも「もったいない精神」から生まれた文化のひとつだと思います。
中古車とレンタカー、どっちがベター?
オーストラリアは言わずと知れた車社会。2、3台所有している世帯も多く、夕方になると自宅前の道路には路上駐車がずらりと並びます。日本と違い道幅に余裕があるので、駐車していてもとくに気にならないのかもしれません。最近では、家内もガレージから車を出し入れするのが面倒で、よく路上駐車しています。
今、僕が乗っている車はレンタカーです。中古車を買うかレンタカーにするか。これも友人のアドバイスが役に立ちました。
オーストラリアで中古車を購入する場合は、日本のような中古車専門店がないので、ほとんどの人がフェイスブックのマーケットプレイスで探します。購入までがとても簡単なので、友人には「注意しろ」と口すっぱく言われました。実車を見て気に入れば即決しがちだけど、一見しただけではその車に欠陥があるかなんて判断できないというわけです。
これは余談ですが、じつは僕の自転車は現地のマーケットプレイスで購入しました。でも、買った直後にタイヤのパンクが見つかって……、結局、自分で修理することに。自転車なら諦めますが、車であれば1万ドル以上(100万円以上)の買い物です。メルボルンの物価が日本の倍くらいですから、1万ドルは現地の感覚だと、日本の約50万円くらい。この価格帯の車だと走行距離25万kmとか、30万kmオーバーとかの中古車ばかりなので、いつ止まるかは予測不能です。
かと言って価格が高い車を購入しても、日本へ帰国するまでに果たしてリセールが成立するかのかどうかも不安。いろいろと考えた末、レンタカーを選ぶことにしました。契約期間は1年。借りたのはトヨタ車ですが、定期的に別の車に乗り換えられるようなので、それもいいかなと思っています。車はまさに日常生活の足なので故障すれば大きなストレス。その点、レンタカーであれば補償もフルプロテクトされていて安心です。
オーストラリアでは郊外に向かうフリーウエイで車がよく止まっています。その光景を見ていると、つくづく中古車選びもチキンレースのようだなと思います。故障で止まる前に売り抜ければ勝ちみたいなところもなきにしもあらずですから。
もちろんそういうこともすべて理解したうえで、マーケットプレイスを利用するのだから、これもまたお国柄ということなのかもしれません。
次回は、ちょっと困惑したメルボルンの冬事情!
((nishida’s column))
メルボルンのおすすめスポットをご紹介!「オーストラリア・イスラミック・センター」
The Australian Islamic Centre設計はグレン・マーカット。モスクの天井にカラフルな三角形の天窓が配置されたモダンなデザインが印象的だ。
profile |
西田 司 osamu nishida1976年、神奈川生まれ。使い手の創造力を対話型手法で引き上げ、様々なビルディングタイプにおいてオープンでフラットな設計を実践する設計事務所オンデザイン代表。東京理科大学准教授、ソトノバパートナー、グッドデザイン賞審査員。主な仕事として、「ヨコハマアパートメント」「THE BAYSとコミュニティボールパーク化構想」「まちのような国際学生寮」など。編著書に「建築を、ひらく」「オンデザインの実験」「楽しい公共空間をつくるレシピ」「タクティカル・アーバニズム」「小商い建築、まちを動かす」。 |
|---|